ゼノンのパラドックス(ver2.0)
こんにちは、どっふぃーです。
皆さん、「ゼノンのパラドックス」というものをご存知でしょうか。
ギリシアの哲学者ゼノンが連続性(運動)を否定するための主張として用いた論で、最も有名なのは「アキレスと亀」のお話でしょうか。
知っている方も多いと思いますが念のため簡単に話を書いておくと
「英雄アキレスと亀が100m走をするとしよう。アキレスの方が足が速いのは明らかなのでアキレスは亀に50mのハンデを上げることにした。そこで亀は50m、アキレスは100mを走ることになり、亀の方が50m前からスタートすることになった。
さて、レースが始まるとアキレスは亀に追いつこうと走っていく。アキレスが50m走った時に、亀は5m走っていた。アキレスはさらに5m走ったが、亀はその間に50cm走っていた。アキレスは何とか追いつこうと50cmまた走ったが、亀はその間に5cm走っている。アキレスが5cm走っても亀は0.5cm先にいる。
おかしい。アキレスが何回亀に追いつくよう走っても、差が縮まるだけでいつも亀が少し前にいる。何度同じことを繰り返そうがアキレスはいつまでも亀に追いつけないではないか。」
文章や数値設定は適当ですが概要はこんな感じですね。
こういう議論をすることで、ゼノンはこの世界に運動というものは存在せず、ただ個々の止まった瞬間があるだけなんだと主張したわけです。〇〇秒後に〇〇m進む、というように考えるとアキレスは亀に追いつけなくなっちゃいますからね。
ただアキレスが亀の少し後ろにいる瞬間と、アキレスが亀を少し抜かした瞬間があって、そのようなものが移り変わっていくだけなのです。
さて、この議論を皆さんは否定できますか?
意外と難しいと思います。何なら「いつまでも」という言葉の解釈によっては完全に正しいことを言っているような気すらしてきて、運動が存在しないというのも微分法の考えと同じような感じなのであながち的を射ている。
流石に1日後も1年後も追いつけないと言われると嘘だろ!って突っ込まざるを得ませんが、それ以外の点は明確に間違っているというポイントは僕には指摘できなかったですね。
そこで本日やってみたいことがこちら。
「ゼノンのパラドックス的なことを言ってみんなを騙したい!」
はい。僕は警察より怪盗に憧れるタイプなので、こういうオシャレな詭弁を見ると自分もやりたくなってしまいます。
そもそも素晴らしい議論をしているのに結論が「アキレスは亀に追いつけない」って何ですか、どうでも良すぎる。
無限に物事を分割することで直感に反することが主張できる、というポイントだけを拝借して、もう少し面白い結論を導き出したいなというのが今日のテーマです。
例えばこんなのはどうでしょうか。
「大谷翔平のホームランをスロー映像で見てみよう。すると最初の5コマぐらいはホームベース近くを飛んでいるはずである。
僕は野球未経験であり、当然ホームランなど打てないが、弱い球ならバットで打って前に飛ばすことはできるだろう。
すると、大谷でも僕でも最初に弾が出発した地点はホームベースの上に変わりない。僕は全てを再現することは無理だが、最初の5コマぐらいなら大谷のホームランの軌道を再現することはできるだろう。
大谷の打球と僕の打球は全く同じように最初の瞬間は動いている、ということは次の一瞬も同じように動くはずである。
では大谷の打球と僕の打球が同じように動かなくなる一瞬はいつ来るのか、来ないとすると僕もホームランが打てるということである。」
大嘘すぎる。打てません。何でかは知らんけど。
ちょっとエッセンスだけを汲み取って論理を捨て過ぎましたかね。
もう少しまともなことを言いましょう。
「今僕が書いているこの言葉は、生まれた瞬間には知らなかったものであるから、誰かから、あるいは本など何かから学習したものである。
言葉は意思疎通のためのツールであるから、言葉を使う際に使った人と使われた人は大体同じようなことを想像するだろう。(全く同じではないにせよ意味もなく新しいものができたりはしない)
さて、そう考えると、僕が使っている言葉は、僕の親やその世代が使っていた言葉によって作られているはずである、さらには親世代が使っていた言葉は祖父母の世代に影響されており、どんどん遡ることができる。
こうなると今の言葉は縄文時代とかの言葉を真似して作られているわけだが、それはつまり縄文時代にあるような言葉をめちゃくちゃ上手く組み合わせればパソコンやSNSといった単語の意味が説明できるということである。」
ギリギリ嘘とは言えないんじゃないでしょうか?言葉づくり屋さんがいるわけではないので既存の言葉での説明を繰り返して今の言語が作られているのは間違いとも言い切れない気がします。
それでは試してみてください。「縄文時代語彙でSNSを説明してみた」
精神論にも手を出してみよう。
「今僕は何もやる気が出ない。しかし今後やる気が出ないとすると何もできないわけだがそうすると僕は死んでしまう。
死なないためにはいつかやる気を出さないといけないが、当然何もないところからやる気は湧いてこないためやる気を出すためにはやる気を出すようなやる気が必要である。
これを無限に繰り返していくと現時点でやる気がないなどということがあろうはずもない、つまり僕には今を含めていつだってやる気があったのである。」
そうか、僕にはやる気があったのか。
ちなみにこれを論破するための概念として「やる気スイッチ」が生み出されたと言われています。
嘘です。
ところで3つ書いたところでふと思いましたが、バタフライエフェクト(蝶の羽ばたきが竜巻を起こすようなことがあるか?という議論)とゼノンのパラドックスって思想が近いかも知れませんね。
100m走程度の話であれば運動の理論によって説明できますが、現実世界で起こる出来事は様々な要因が絡み合ってできているため、単純な1つ2つのパラメータによっては説明がつきません。
起こった出来事に対して、全て少し前の瞬間からの因果でできていると考えるようでは、あまりに不可解な結論が導き出されてしまう、ということを察して、ゼノンは現実とは不動の瞬間を集めたものに過ぎないと考えたのかも。
そう考えると一気にこのエピソードの深みが増してきましたね。
運動というものを否定しているというより、運動を考えるような理論体系で全てが説明できるとは思えない、現実ありきで我々は生きないといけないんだというのがゼノンのパラドックスなんじゃないでしょうか。
つまりゼノン先生の言いたいことは、世の中実際に起こったことを見て理由を分析することは簡単でも、それを活かしてこれからの未来を思い通りに動かすのはなかなか上手くいかないものだから、あるがままに今の瞬間を生きた方がいいよってことだったのか。
いい話だなぁ。
勝手にいい話にして勝手に納得したところで今日はここまで。次回は多分現実ソフトウェア化計画の話をすると思います。
お楽しみに!

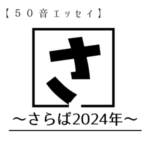








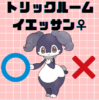










ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません